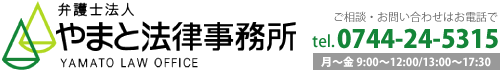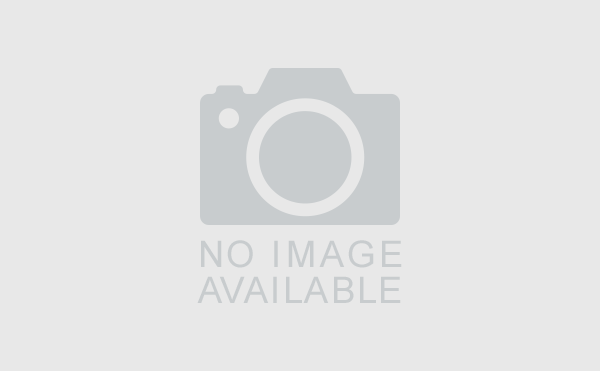SNSや掲示板サイトでの誹謗中傷に対する対応①(弁護士 松ケ下裕介)
1 はじめに
現在SNSの利用が拡大し、インターネット上での誹謗中傷も増加し、社会問題となっています。
このような誹謗中傷の被害にあった場合、どのような対応策があるのか、その概要について解説していきたいと思います。
2 被害回復のための対応策
まず、インターネット上で、誹謗中傷があった場合、被害を回復するための大まかな方向性としては、2つあります。
1つ目は、①誹謗中傷に関する情報を削除してもらう方法です。
2つ目は、②書き込み等をした者(以下、「発信者」といいます。)への責任を追及する方法があります。
これらの方法のうち、①の方法は、発信者を特定できない状態であっても行うことができ、また、被害拡大を抑えることができるため、まず最初に考えるべき手段であるといえます。
また、再発防止の観点から、②の方法も検討すべき手段といえます。
なお、上記2つの方法を行う前提として、誹謗中傷された証拠として、ウェブサイトのURLやスクリーンショット等を残しておくことも重要です。
3 削除の具体的手段
①の削除を求める場合、まず、請求する相手としては、ウェブサイトを運営する管理者やサーバの管理者となります。
削除を求める法的根拠としては、人格権に基づく妨害排除請求権としての差止め請求権であり、2025年4月1日施行の情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)に基づくものではありませ ん。
削除してもらう具体的な手段としては、
ア 管理者への直接削除を求める方法
(ウェブフォーム等からの削除依頼や、旧プロバイダ責任制限法関連ガイドラインの書式を使った郵便での請求等)
イ 民事保全を利用する方法(削除の仮処分)
ウ 訴訟による方法(削除訴訟)
が考えられます。
なお、上記ア~ウのどの手段を利用するかについては、誹謗中傷の内容や管理者の対応等の事情により異なります。
4 発信者への責任追求
(1) 発信者の特定
②の発信者への責任を追及するためには、まず、責任を追及する対象である発信者の素性を明らかにする必要があります。そして、素性を明らかにする手段としては、「発信者情報開示請求」という手続きがあ ります。
「発信者情報開示請求」とは、情報流通プラットフォーム対処法第5条に規定されており、発信者に関する情報を通信に関与した通信事業者等に求めることができる権利です。
「発信者情報開示請求」を行う具体的な手段としては、
ア 裁判外での行使(裁判を利用せず、直接、通信事業者等へ情報を求める)
イ 民事保全を利用する方法(仮の地位を定める仮処分)
ウ 発信者情報開示命令(仮処分より使える幅が広く、訴訟よりも迅速な審理が可能)
エ 訴訟
が考えられます。
もっとも、上記方法により、発信者情報開示請求を行ったとしても、発信者の特定まで至らないケースも存在します。
(2) 発信者への民事上の請求
上記請求により、発信者を特定できれば、不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)や謝罪広告を求める原状回復措置(同法723条)等を行うことが考えられます.
もっとも、誹謗中傷での権利侵害に対する損害賠償請求の裁判では、大きな金額が認められないことも多く、弁護士費用を下回る可能性もありますので、その点を考慮しつつ上記手段を検討する必要はありそうです。
(3) 刑事上の責任追及
インターネット上の誹謗中傷が、社会的評価を低下させたり、危害を加えたりするようなものである場合は、名誉毀損罪や脅迫罪、侮辱罪、著作権法違反等に該当する可能性があります。
そのような場合には、警察への相談や刑事告訴等の手段により、処罰を求めることも考えられます。
5 おわりに
以上が、インターネット上の誹謗中傷に対する対応策の大まかな解説です。
誹謗中傷への対応を考える上では、警察庁のHP上の「インターネット上の誹謗中傷等への対応」(https://www.npa.go.jp/bureau/cyber/countermeasures/defamation.html)についても参考した上で、上記対応策を検討することになりそうです。
もっとも、誹謗中傷の被害に遭わないため、安易に個人情報を他人に教えず、インターネット上にも載せないといった、事前の予防対策も重要です。
各対応策の詳細や情報流通プラットフォーム対処法の改正点については、次回以降に解説していきたいと思います。