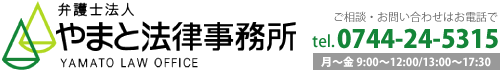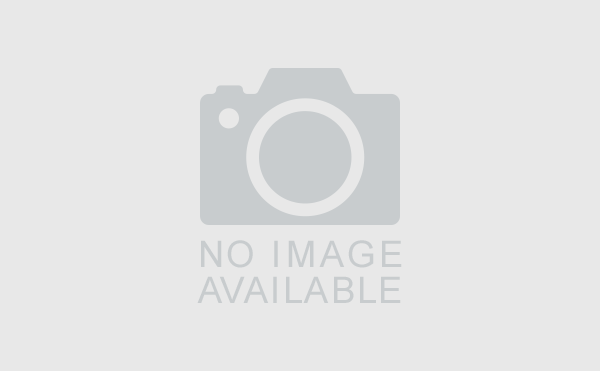養子と代襲相続(弁護士 井上泰幸)
前回(2024年9月)のブログで相続の基礎知識をご紹介しましたが、その後新しい裁判例が出ましたので、これを紹介したいと思います。
最高裁第二小法廷判決令和6年11月12日では、「被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系尊属でない者は、被相続人の兄弟姉妹を代襲して相続人となることができない」と判示しました。
この裁判例の事案は、図のAとBが従兄弟の関係にあったところ、Aの子Cが生まれた後にBの母とAが養子縁組をしたことで法律上兄弟になったという関係性のものです。その後、Aが死亡した後、Bが死亡したというものです。そして、この場合にCはBの兄弟の子として(代襲)相続権を有するかが問題となりましたが、上記のとおり、最高裁は相続人となることを認めませんでした。
この裁判例を理解する上で、前提として、養子の子に(代襲)相続権が認められるかという論点があります。まず、養子縁組の効果として、血族関におけるのと同一の親族関係を生じるというものがあります(民法727条)。しかし、縁組以前に生まれた養子の直系卑属と養親との間には親族関係を生じないとされています(大審院判決昭和7年5月11日)。そして、代襲相続に関して、被相続人の直系卑属でない者は代襲相続しないと定められています(民法887条2項但書)。つまり、これまでも養子の子の出生と養子縁組の前後で代襲相続の有無が区別されていました。養子縁組より前からいる養子の子には養親の代襲相続権がなく、養子縁組後に生まれた子には養親の代襲相続権があることになります。
今回の裁判例の原審では、民法887条2項但書の「被相続人の直系卑属でない者」を「被相続人の傍系卑属でない者」と読み替えるのが相当という判断をしたようですが、最高裁は養子縁組以前に生まれた養子は養親との間に血族関係を生じることはないという大審院判決を敷衍して、養子縁組以前の子には養親の相続権はないと判断したものと考えられます。
今回は最新の裁判例の紹介をしましたが、これだけでも複雑だと思いますが、相続事件ではさらにいろいろな制度があり、専門的な法知識が要求されます。お困りの場合には、是非ご相談ください。
画像-1024x576.jpg)